以前、心療内科で【バウムテスト】を受けたことを書きました。⇒こちら
それから数ヶ月経過した今、改めてバウムテストについて調べてみました。
今回はルネ・ストラの解釈についてまとめました。
一般的な解釈のまとめはこちら。
『バウムテスト』ルネ・ストラをオススメ!
今回、難解なバウムテストの解釈をまとめるにあたり、この書籍を購入しました。興味本位で読み始めましたが、知識は深まりました!

オススメします!
このブログ記事について
バウムテストの解釈については諸説あり、現在も研究が進んでいる分野です。よって医療従事者や研究者によっては、当記事の内容と異なる解釈となっている場合も考えられます。
当記事はあくまで前述の『バウムテスト』ルネ・ストラの著書をまとめたものです。
また、大変参考になったサイトを最後に1つ紹介させていただきます。
この記事の内容は、実際の治療等において必ずしも合致した解釈や見解にはならないこともありえますのでご理解ください。
うつ状態にある場合の描画

バウムテストは躁うつ病、統合失調症(破瓜病、緊張病、妄想病)、神経症、認知症など様々な場面で用いられます。
1枚だけ描くもの、2枚3枚描くもの等、描いた後に質問を受けるもの(PDIと言います。)など多岐にわたります。
今回は、【うつ状態】であることを前提とした解釈を記していきます。
うつ状態における描画の特徴
- バーミセル状※の短い根
- 波打つ筆圧の弱い描線
- かなり傷ついた幹
- 弱々しく震え、何度もなぞって描いたように見える描線
- 木の構成要素が欠如していることが多い
- 小さな木
- 花や実がない
- ほとんど単線で描かれた枝
※バーミセル・・・細いパスタの一種。バーミセリともいう。
描画サインのカテゴリー分類
描かれた木の絵のそれぞれの特徴をサインと呼び、ルネ・ストラは15のカテゴリーに分類しました。
- 教示と異なる描画
- 地面
- 根
- シンメトリー構造
- 描線の交叉
- 用紙上の位置
- 樹冠の形
- 陰影
- 幹
- 木の高さ
- 樹冠の長さ
- 樹冠の幅
- 用紙からのはみ出し
- 描線
- 追加項目
各カテゴリーの特徴と解釈

①教示と異なる描画
- 用紙を横長方向に使用している(縦方向に差し出された用紙を横長方向用いた場合)
⇒独立独歩の精神
- 複数の木
⇒子どもっぽい振る舞い
②地面
- 単線の地面ライン
⇒目的に向かって努力する
- 右上がりの地面ライン
⇒情熱
- 右下がりの地面ライン
⇒落胆、高揚感の欠如
③根
- 幹に比べて遥かに小さな根
⇒隠されているものを見たい好奇心
- 幹に比べて遥かに大きな根
⇒強すぎる好奇心
- 幹と同じくらいの長さの根
⇒トラブルを引き起こしかねないほど強い好奇心
④シンメトリー構造
- 斜め上方向の対称(幹を軸として):枝が幹に対して鋭角に、しかも幹の同じ高さから左右の枝が出ている。
⇒攻撃性を抑えようとする努力
- 交互に斜め上方向の対称(幹を軸として):枝が幹に対して鋭角である。左右交互に出ている。
⇒情緒的な負荷に対して引き起こされやすい焦燥感。
⑤描線の交叉
描線の交叉は葛藤や苦悩を意味する。
⑥用紙上の位置
※用紙を縦横方向にそれぞれ4分割する。
- 左に位置する(木全体が左1/4におさまっている)
⇒過去、母のイメージを表現するものに対して両価的な感情を抱いている。
- 右に位置する(木全体が右1/4におさまっている)
⇒権威にすがろうとする。
- 厳密に中央に位置する
⇒日常的な感覚を越えるような厳密さと息苦しさを覚えるような頑なさ。
- 上方に位置する(木全体が用紙の上方1/4におさまっている)
⇒はしゃいだりして抑うつ気分を解消しようとする。
- 下方に位置する(木全体が用紙の半分以下におさまっている)
⇒不満を感じている。
⑦樹冠の形
- 下降する茂み
⇒失望、努力することを放棄する
- 単線の枝
⇒不快な現実から逃げる。又はそうした現実を美化、違うものと思い込む。
- 先端が切られた枝
⇒情緒的な外傷体験
- 木の内部にも木以外の場所にも花
⇒苦しみ、感傷、緊張
- 椰子の木
⇒環境の変化や気分転換を求めている
- 枝垂れ柳
⇒大胆さの欠如、原因のあるなしにかかわらない失望
- 右に広がる樹冠部
⇒しっかりした支えが欲しい。積極的な対人接触を求める
- 左に広がる樹冠部
⇒過去や子ども時代の経験への回帰
⑧陰影
- 執拗に繰り返し塗られた幹に陰影
⇒不安をかき立てる両親との間に見られる深刻な問題。積年の恨み。
- 輪のようにグルグル書きに陰影
⇒子どもっぽい依存、諦め
- 斑点状の陰影
⇒繰り返し夢見ることで紛らわそうとするが、悲しみは消えない。
⑨幹
- 幹にウロ
⇒ダメージの残る失敗だと感じる
- 単線の幹
⇒現実をあるがままに見ることを拒否。そのこと自体は意識している。
- 2本線の幹と単線の枝
⇒現実を見ることはできるが、自分の欲望に合致しない場合には認めない。
- 地面から離れている幹
⇒周囲との接触不良
- 左に傾く幹
⇒攻撃されるのを恐れて閉じこもる
- 右に傾く幹
⇒支えを求める
- 幹の下部が広がっている
⇒自分の環境に確固とした立場を求める
⑩木の高さ
※用紙を縦方向に4等分する。
- 用紙の高さの1/4以下の高さ
⇒依存、未熟さ
- 用紙の高さの2/4以下の高さ
⇒内気
- 用紙の高さの3/4の高さ
⇒環境に対する適応がよい
- 用紙の高さの4/4の高さ
⇒目立ちたがり屋、承認欲求
⑪樹冠の長さ
- 樹冠部よりも大きな幹
⇒刹那的な生き方。多動的傾向と焦燥感
- 樹冠部と同じ高さの幹
⇒何とかバランスをとろうとする。周囲の期待に応えようとする。
⑫樹冠の幅
※用紙を横方向に4等分して樹冠の幅を測る。
- 用紙の1/4の幅
⇒自分の能力に対する疑い
- 用紙の2/4の幅
⇒自分の価値をそれほど認めていない
- 用紙の3/4の幅
⇒能力的に優れているが、それを表現するのがやや困難である。
- 用紙の4/4の幅
⇒話し好きで周囲の注意を惹き、自分の存在を周囲にアピールする。
⑬用紙からのはみ出し
- 用紙の左側にはみ出している樹冠
⇒様々な理由により満足させてくれなかった母親に対する愛着と攻撃性。
- 用紙の右側にはみ出している樹冠
⇒他者をコントロールしたい欲求、対人接触の困難さ。
- 上方へのはみ出し
⇒万能感で劣等感情を補償しようとする。
- 用紙の下縁からはみ出した幹
⇒見捨てられ感。やさしさの欲求
⑭描線
- 樹冠が棒状の描線で描かれている
⇒攻撃的発散
- 幹や地面が矢のような鋭い描線で描かれている
⇒日々の生活における欺瞞と非難。自己や他者への非難。
- 幹が筆圧の弱い描線で描かれている
⇒自分を肯定したり、自由に振る舞うことが怖くてできない。
- 樹冠が筆圧の弱い描線で描かれている
⇒鋭い感受性。影響を受けやすい。
- 幹の輪郭線が切れ切れに描かれている
⇒自殺。恐怖や悩みを隠そうとして無気力な態度を取る。
⑮追加項目
- 地面に映る木の影
⇒何らかの傾向を排除する
- 枝がない
⇒接触困難。拒否的あるいは防衛的態度
まとめ
このように描かれた絵の特徴は非常に多く、今回抜粋し、まとめたのはほんの一部に過ぎません。中には難解な表現もあり、素人がカンタンに理解できるものではありませんね。。。

むずかしいナァ
解釈にはいろいろな読み方があります。
今回はルネ・ストラの書籍を参考にしつつ、サインがわかりやすく分類・解説された【バウムテストの森】さんも大いに参考にさせていただきました。
サインは組み合わせて照合する必要があるとされていて、様々な解釈ができるひとつの要因となっています。
何かの参考になれば幸いです。
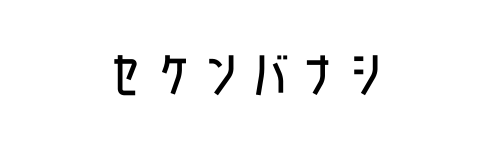


コメント